- 「私の障害について」はどうやって書くの?
- 配慮事項を書くときのポイントを知りたい
書きすぎて落とされないか、逆に書かなさすぎて配慮されないのではないか……。
この「正解のわからなさ」が不安になりますよね。
僕自身は精神障害の当事者でありながら、フリーランスのWebライターとして働いています。
そのため、自社でも障害者採用を行なっている障害者に特化した転職エージェント「dodaチャレンジ」![]() の担当者に話をうかがいました。
の担当者に話をうかがいました。
そのなかでおすすめいただいたのは「以下3つのポイントを押さえる」ことです。
- 自分の苦手なことを整理する
- 対処法や配慮事項を具体的に書く
- 配慮事項が対処法より大きくならないようにする
記事の後半では、これらを踏まえてWebライターの僕が書いた実際に使えるテンプレート(精神障害・ASD・ADHD向け)紹介します。
ぜひ最後まで読んでみてください!
「私の障害について」を書くうえで大切な3つのポイント

「私の障害について」は、症状を書くだけの欄ではなく、採用担当者に安心して働けるポイントを理解してもらうための大切な情報です。
そのため、以下の3つを意識できるかどうかで、印象が大きく変わります。
- 自分の苦手なことを整理する
- 対処法や配慮事項を具体的に書く
- 配慮事項が対処法より大きくならないようにする
それぞれ詳しくみていきましょう。
自分の苦手なことを整理する
苦手なことが自分でわからなければ、対処法や配慮事項を具体的に書くのは難しいです。
対処法や配慮事項もあいまいになり、結果として採用側に正しく伝わらないかもしれません。
そのため、まずは「障害特性ゆえに苦手なことを、あなたのなかで整理する」ところから始めましょう。
例えば、あなたが以下のことで悩んでいたとします。
- 突然の電話対応があると、しばらく手が止まってしまう
- 仕事を進めているときに別の業務をお願いされると、頭が真っ白になる
- 仕事の納期が突然早まった場合、不安感に襲われる
これらの3つで共通しているのが「臨機応変な対応」。
ここを配慮してもらえるだけでも、かなり働きやすくなるのではないでしょうか。
このように、個々の悩みを1つの特性へまとめることが大切。
結果として、対処法や配慮事項がわかりやすくなります。
対処法や配慮事項を具体的に書く
整理した苦手な点がわかったら、次に 「どのように対処しているか」 と「どんな配慮があれば安定して働けるか」 の2つを具体的に書きましょう。
このとき「なるべく具体的に書く」のがポイント。
先ほどの例で言いますと、以下のようになります。
対処法(自分で行っていること)
- 業務を依頼されたときに、納期を毎回確認している
- 手帳に毎朝その日のタスクを書き出し、優先順位をつけている。そしてタスクごとにふせんに書いてパソコンの周りに貼り、できたものから捨てている。
配慮事項(お願いしたいこと)
- 差し込みで仕事が入ったときは、どの範囲でどのタイミングでやればいいのかを教えてほしい。
上のように具体的に書くと、一緒に仕事をする姿をイメージできますよね。
そして、「この人は苦手を理解し、自分なりに対処している」 というのが伝わるため、採用する人から良い印象を持ってもらえます。
 じんと
じんと前職はもちろん、就労移行支援・就労継続支援でのエピソードもおすすめです。
配慮事項が対処法よりも大きくならないようにする
一方で、気をつけたいのが「配慮事項が対処法より大きくならない」こと。
配慮事項のほうが多いイメージを持たれてしまうと、「わがままな人だな」と見た人から思われるためです。
以下の2つを心がけ、「自分なりに頑張って対処はしてるんだな」という印象を持ってもらいましょう。
- 特性と対処法がなるべく関連づいている
- 配慮事項のあとに対処法を書く
とはいえ、「配慮事項の数が多い=悪い」というものではありません。
「大きく見せないように工夫する」だけでも、見た人からの印象は大きく変わります。
そして、ここでおすすめしたいのが、「障害者雇用に特化した転職エージェント」の活用。
何人もの転職をサポートしたアドバイザーが、「私の障害についての見せ方」を一緒に考えてくれますよ!
なかでも「dodaチャレンジ」は、運営元のスタッフのうち6割以上が障害者雇用。
転職支援はもちろん、自社での採用の経験に基づいて「面接官目線のアドバイス」が受けられます。
もし気になったら、下のボタンから公式サイトをのぞいてみてくださいね!
\採用目線でのアドバイスが魅力◎/
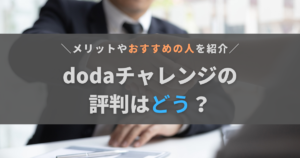
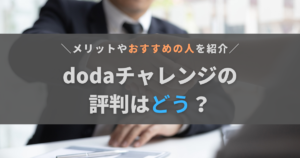
「私の障害について」のテンプレート3選


ここまでの内容踏まえて、dodaチャレンジの担当者に監修いただきながら「私の障害について」のテンプレートを以下3つの場合で作成しました。
その他の障害や配慮事項が異なるときは、このテンプレートをもとにあなたの対処法や配慮事項に書き換えてくださいね!
- 精神障害(うつ病)
- ASD(自閉スペクトラム症)
- ADHD(注意欠如・多動性障害)
精神障害(うつ病)の人の例
まずは、精神障害の例としてうつ病の場合を紹介します。
障害概要
- 診断名:うつ病
- 手帳:精神保健福祉手帳 3級
- 通院 / 服薬:月1回(水曜日午前)/ 朝晩各1回
- 就業許可:有
特性・対処法
私はうつ病を患っており、体調の波が不安定になることがございます。ですが、安定して働けるように下記3点を心がけ、週5日8時間問題なく動けております。
- 起床、就寝時間を一定にする
- 通院や服薬を欠かさず行う
- 特にデータ入力やチェックなどの集中しやすい業務は過集中になりやすいため、適宜休憩をとる
配慮事項
前述の特性に対して自己対処は行なっておりますが、自己対処だけでは難しい下記3点についてご配慮いただけますと幸いです。
- 生活リズムを一定にし、高いパフォーマンスを継続するために残業の配慮をお願いいたします
- 通院のため、月1回水曜日にお休みをいただけますと幸いです
- 過集中になっている様子が見えた場合は、お声がけいただけますと切り替えがしやすいです
ASD(自閉スペクトラム症)の人の例
続いて、ASD(自閉スペクトラム症)の人の例です。
障害概要
- 診断名:自閉スペクトラム症(ASD)
- 手帳:精神保健福祉手帳 3級
- 通院 / 服薬:月1回(水曜日午前)/ 朝晩各1回
- 就業許可:有
特性・対処法
私は自閉スペクトラム症と診断されており、以下のような特性があります。
- マルチタスクが苦手
- あいまいな指示を汲み取るのが難しい
- 過集中になる(主にデータ入力業務)
これらに対し以下の対策を立て、業務を遂行しております。
- 毎朝始業前にタスクを整理し、優先順位を決めている
- わからない箇所はその場で質問をし、メモを取るようにしている
- 特にデータ入力業務のときは、適宜休憩を取るようにしている
配慮事項
前述の特性に対して自己対処は行なっておりますが、自己対処だけでは難しい下記4点についてご配慮いただけますと幸いです。
- 通院のため、月1回水曜日にお休みをいただきたいです
- 差し込み業務があるときは、現在のタスクとどちらを優先すべきかご教示いただけますと幸いです
- 指示に具体的な期限や判断基準を入れていただければ、業務をスムーズに進めやすいです
ADHD(注意欠如・多動性障害)の人の例
最後に、ADHD(注意欠如・多動性障害)の人の例を紹介します。
障害概要
- 診断名:注意欠如・多動性障害(ADHD)
- 手帳:精神保健福祉手帳 3級
- 通院 / 服薬:月1回(水曜日午前)/ 朝晩各1回
- 就業許可:有
特性・対処法
私は注意欠如・多動性障害と診断されており、以下のような特性があります。
- マルチタスクが苦手
- 打ち合わせなどの時間を忘れてしまう
- 他の物事に気を取られ、ケアレスミスが生じる
これらに対し以下の対策を立て、業務を遂行しております。
- 毎朝始業前にタスクを整理し、優先順位を決めている
- 5分前に通知機能をつけ、通知が鳴ったら作業を中断して準備をする
- 完了後すぐに提出せずに、1度チェックする
配慮事項
前述の特性に対して自己対処は行なっておりますが、自己対処だけでは難しい下記3点についてご配慮いただけますと幸いです。
- 通院のため、月1回水曜日にお休みをいただきたいです
- 差し込み業務があるときは、現在のタスクとどちらを優先すべきかご教示いただけますと幸いです
- 細心の注意を払っておりますが、どうしても抜けもれが生じることがあります。後の工程にご迷惑をおかけするのを防ぐため、ダブルチェックをお願いしたいです
「私の障害について」の書き方と関連してよくある質問


最後に、「私の質問について」の書き方とに悩む人が感じやすい質問にお答えします。
書類作成や面接で迷いやすいポイントなので、ぜひ参考にしてみてください。
まとめ:「私の障害について」のテンプレートを活用し、社会復帰を成功させよう


この記事では、「私の障害について」を書くときのポイントとテンプレートを3つずつ紹介しました。
改めて、3つのポイントを振り返りましょう。
- 自分の苦手なことを整理する
- 対処法や配慮事項を具体的に書く
- 配慮事項が対処法より大きくならないようにする
これらを取り入れた結果、私の障害については「安心して働くための提案書」へと変わります。
この3つのポイントとテンプレートを活用し、焦らずにあなたのペースで内定をゲットしてくださいね!
そうは言っても



書き方、本当にこれで大丈夫かな……
という人もいるでしょう。
そんなあなたには「障害者雇用に特化した転職エージェント」の利用がおすすめ。
専任アドバイザーが「あなたの配慮事項の見せ方」を一緒に考えてくれるので、書類でお見送りになる可能性がグンと減りますよ!
なかでも自社で特例子会社を持ち、障害者雇用の採用を行なっている「dodaチャレンジ」![]()
![]()
無料で登録できますので、この機会にぜひチェックしてみてくださいね。
\採用目線で寄り添うサポート◎/
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
ではでは、今日も生きててえらい!

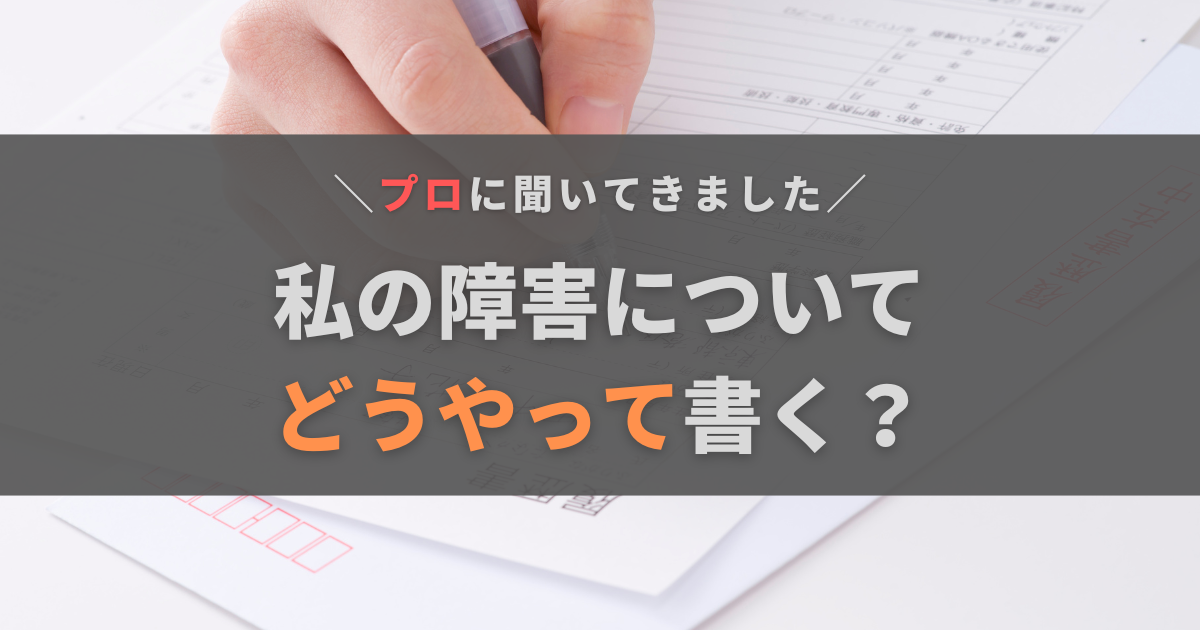

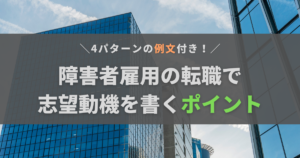
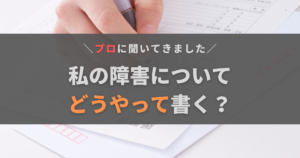
コメント